|
スライド
ショー
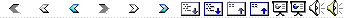 |
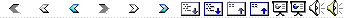 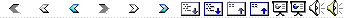 |
 ノート ノート |
|
スライド
ショー
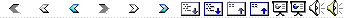 |
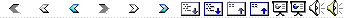 |
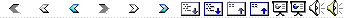 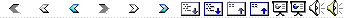 |
アウトライン |
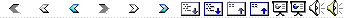 |
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|
|
|
6
|
|
|
7
|
|
|
8
|
|
|
9
|
|
|
10
|
|
|
11
|
|
|
12
|
|
|
13
|
|
|
14
|
|
|
15
|
|
|
16
|
|
|
17
|
|
|
18
|
|
|
19
|
|
|
20
|
|
|
21
|
|
|
22
|
|
|
23
|
|
|
24
|
|
|
25
|
|
|
26
|
|
|
27
|
|
|
28
|
|
|
29
|
|
|
30
|
|
|
31
|
|
|
32
|
|
|
33
|
|
|
34
|
|
|
35
|
|
|
36
|
|
|
37
|
|
|
38
|
|
|
39
|
|
|
40
|
|
|
41
|
|